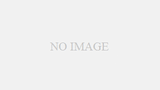1. バックアップは何のため?(目的とゴール)
- 誤操作・論理障害(削除・上書き・マルウェア)からの復旧
- 物理障害(ディスク故障、筐体故障、災害)への備え
- 監査・証跡・法令対応(一定期間のデータ保全)
- テスト/検証(本番相当のデータを用いた再現/検証)
バックアップのゴールは「求める時点のデータを、求める時間内に、安全に戻せる」状態を作ることです。
2. 復旧目標(RPO/RTO)の決め方
- RPO(Recovery Point Objective):どこまでのデータを諦められるか(例:最大15分の欠損まで許容)
- RTO(Recovery Time Objective):どれくらいの時間で復旧できれば業務に耐えられるか(例:2時間以内)
目標設定のコツ: 重要システムは「短いRPO/RTO」を設定し、低重要度はコストとリスクのバランスで緩める。RPO/RTOは監視・復旧テストの実測で定期的に見直す。
3. 方式の種類(サーバー/ファイル/DB/スナップショット)
3.1 サーバー全体/イメージ系
- OS・ミドルウェア含めたベアメタル復旧(BMR)が可能。障害時にサーバー丸ごと復旧が早い。
- 容量が大きくなりがち。重複排除/圧縮・増分永続(Forever-Incremental)採用が一般的。
3.2 ファイル/ディレクトリ単位
- 必要なファイルのみ高速に復旧可能。日次運用の事故対応に強い。
- アプリケーション整合性は別途配慮(停止やVSS/プリ/ポストスクリプト)。
3.3 バックアップレベル
- フル:全データ。復旧は簡単だが時間/容量コスト大。
- 差分:最後のフル以降の変更分。復旧はフル+差分。
- 増分:前回バックアップ以降の変更分。転送量小、復旧はチェーン管理が重要。
3.4 スナップショット(ストレージ/ハイパーバイザ/クラウド)
- 瞬時取得、整合性確保に注意(アプリ整合スナップショット推奨)。
- 同一装置内のみだと災害に弱い。別リージョン/別媒体への複製で堅牢化。
3.5 データベース(DB)
- 物理バックアップ(例:RMAN、xtrabackup):高速・PITR対応しやすい。
- 論理バックアップ(例:mysqldump、pg_dump):移行や部分復旧に便利だが容量/時間が増えやすい。
- トランザクションログ/アーカイブログでPITR(ポイントインタイム復旧)を実現。
4. 整合性の確保(アプリ整合/トランザクション整合)
- アプリ整合(Application-Consistent):DBやサービスを一時クエイセス/フリーズして整合点を作る(例:WindowsのVSS、Linuxはプリ/ポストでフリーズ)。
- クラッシュ整合(Crash-Consistent):電源断相当。ジャーナルで戻せる設計なら可だが、DBは原則アプリ整合推奨。
- トランザクション整合:ログバックアップ+チェックポイントでPITR前提の設計に。
5. 設計の原則(3-2-1・暗号化・Immutable など)
- 3-2-1原則:3つのコピーを、2種類の媒体に、1つはオフサイト/クラウドに。
- 暗号化:保存時/転送時(At-Rest/In-Transit)双方。鍵管理(KMS/HSM)とアクセス権限の最小化。
- イミュータブル(WORM)/オブジェクトロック:ランサム被害時の最後の砦。
- ゼロトラスト/分離:バックアップ管理プレーンを本番から分離、MFA・特権アカウント管理。
- タグ/ポリシー化:重要度別にテンプレ化(例:Gold/Silver/Bronze)。
6. スケジュールと保持(世代管理・ライフサイクル)
- 例:金曜フル+平日増分、ログは15分〜1時間ごと。
- 保持例:日次30世代、週次8世代、月次12世代、年次7世代(会計・監査要件に合わせ調整)。
- ライフサイクル:高性能ストレージ→低コストアーカイブへ自動階層化。
- バックアップウィンドウ:業務影響を避ける時間帯に設定、スロットリング活用。
7. 日々の運用チェックリスト
- 前日ジョブの結果確認(成功/失敗/警告、成功率のトレンド)
- 失敗原因の切り分け(ネットワーク、権限、VSS/スクリプト、容量不足)
- バックアップ先の使用率(重複排除率、圧縮率、アーカイブ移行の進捗)
- ログ・アラート監視(過剰リトライ、長時間化の検知)
- 重要サーバーの整合性(アプリ整合で取れているか)
- PITR前提のシステムはログ断絶がないか(チェーン健全性)
- オフサイト/クラウド複製の到達確認
- 復旧演習の計画/実施(毎月ミニ演習、四半期で全体演習)
- 変更管理(サーバー追加・移行時のポリシー適用漏れ防止)
8. 復旧手順とテスト(DR/BCPを意識)
- 復旧ランブック(役割分担、連絡系統、優先順位、RTO/RPO、手順書リンク)を整備。
- テストの種類:単一ファイル復旧、アプリ単体復旧、サーバーBMR、サイト全体DR切替。
- 評価指標:実測RTO/RPO、失敗原因、改善アクション、再発防止。
9. 性能・容量・ネットワークの勘所
- ボトルネック可視化:ソース/ネットワーク/ターゲット/重複排除装置のどこで詰まるか。
- 増分永続+合成フルでウィンドウ短縮。可能なら変更ブロック追跡(CBT)を活用。
- 帯域制御/並列度のチューニング、遠隔地はWAN最適化や圧縮を検討。
- 容量見積り:初回フル+日次変更率×保持期間−重複排除効果。
10. 現場で使う具体例(Windows/Linux/DB)
10.1 Windows Server(VSS)
- VSS対応のバックアップでアプリ整合(SQL Server/Exchange等)。
- サービス停止が難しい場合はVSSフリーズ、ログバックアップ併用でPITR。
- 例:
SQL Serverは FULL/DIFF/LOG で運用、COPY_ONLYで一時フル取得しチェーン影響を回避。
10.2 Linux(LVM/スクリプト)
- LVMスナップショット→ファイル/ブロック転送で整合点を確保。
- プリ/ポストスクリプトでアプリをクエイセス(例:
systemctl stop app→ 取得 →start)。
10.3 Oracle
- RMANで物理バックアップ+アーカイブログ。PITR、表領域単位復旧、ブロックメディアリカバリ。
- 2台構成/共有ディスク(SEHA等)の場合は整合スナップ+RMANの組み合わせが有効。
10.4 MySQL/MariaDB
- 論理:
mysqldump --single-transaction(InnoDB想定)で整合取得。 - 物理:xtrabackupで無停止・差分・PITR対応。
- バイナリログでポイントインタイム復旧。
10.5 PostgreSQL
- ベースバックアップ+WALでPITR。
pg_basebackupやバックアップ製品のプラグインを利用。
11. ドキュメントとガバナンス
- 資産台帳:バックアップ対象一覧(役割、重要度、RPO/RTO、担当、ポリシー名)。
- 命名規則:ジョブ/ポリシー/保存先/タグの規則統一。
- 変更管理:新規サーバーは自動で「標準ポリシー」が当たる仕組み(タグ/OU連動)。
- 監査ログ:取得・復旧・削除・鍵操作の履歴保存。
- 教育/演習:新人向けオンボーディング資料と年次演習。
12. よくある質問(FAQ)
Q. スナップショットはバックアップの代わりになりますか?
A. 同一装置内のみのスナップショットは災害や装置故障に弱く、代替にはなりません。別媒体/別リージョンへの複製やエクスポートと組み合わせて使いましょう。
Q. どの程度の頻度で復旧テストをすべき?
A. 重要システムは月次で部分復旧、四半期でBMR/DRテスト、年次で全体演習を推奨。実測でRTO/RPOを確認し、改善します。
Q. ランサム対策の要点は?
A. イミュータブル/WORM、管理プレーン分離、最小権限、ネット分離(エアギャップ/隔離アカウント)、検知連携(EDR/SIEM)です。
まとめ
バックアップは「方式」よりも「復旧できるか」が本質です。RPO/RTOを起点に、3-2-1と整合性、運用監視、定期的な復旧テストまでを一気通貫で設計・運用しましょう。